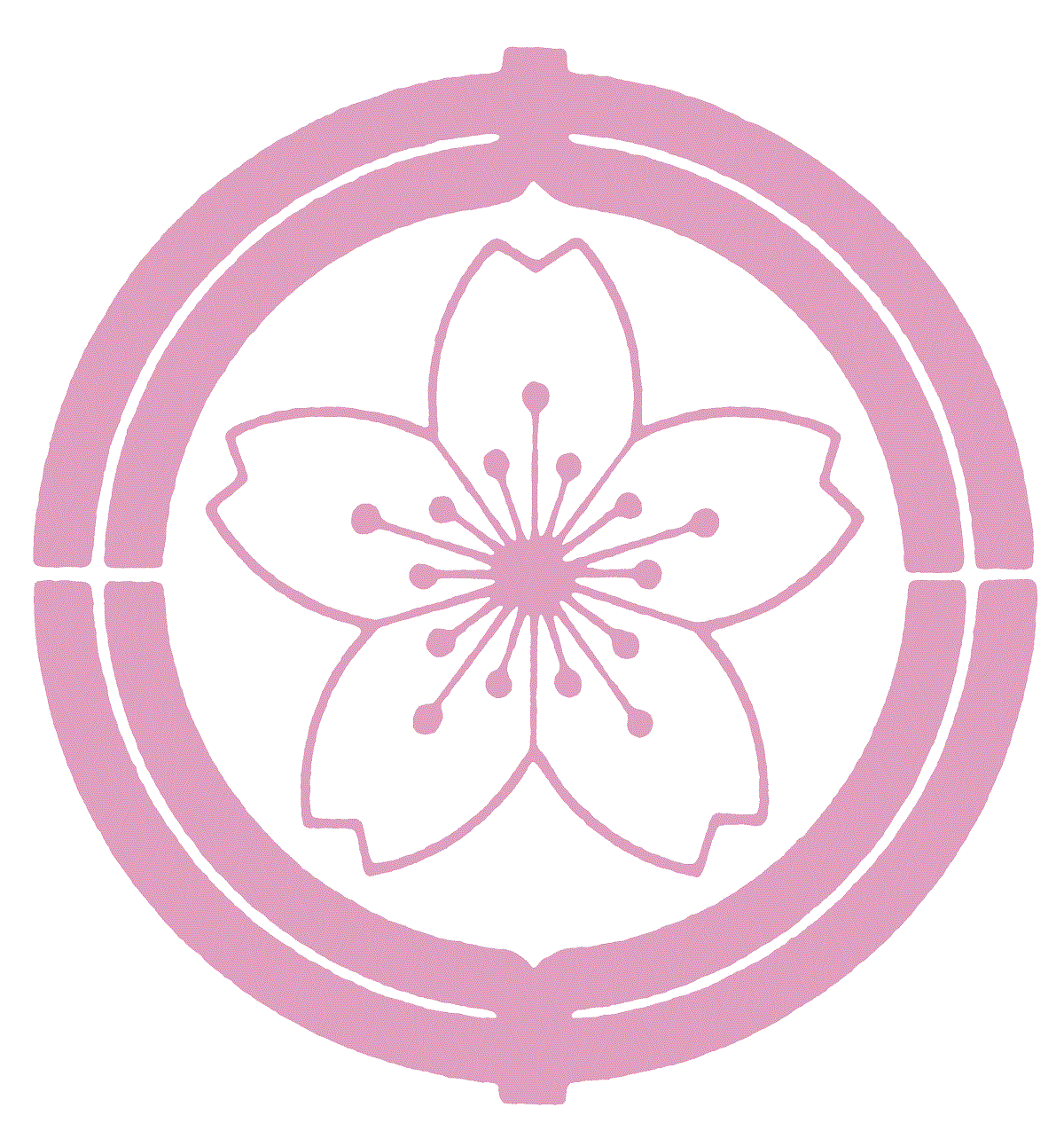優等生から「悪役」へ―「横綱白鵬"孤独"の14年」を見て(続)
前の記事で、NHKスペシャル「横綱白鵬"孤独"の14年」を取り上げ、白鵬と双葉山を比較した(以下、写真は同番組から画面を撮影)。
ただ、この記事の中では、あくまで相撲内容に関することだけを取り上げ、意図的に触れなかったことがある。
双葉山が活躍したのは、第二次世界大戦期と重なっていた。双葉山の活躍は――双葉山自身の意図とは何の関係もなかったが――「皇軍無敵の進撃」にたとえられた。双葉山は「国民の英雄」だった。
それに対し白鵬はモンゴル人、つまり、この日本においては「外国人」だった。双葉山と比べると、これが力士としての白鵬に出だしから一種の「ハンデ」として働いたことは確かだ。
●「悪役」朝青龍 「優等生」白鵬
破天荒で、時に傍若無人とも言える振る舞いをする朝青龍に眉をひそめるファンも多かった。ギャフンと言わせる力士はいないのかという声もあったところへ登場したのが白鵬。朝青龍の天下を脅かし始める。「ヒール」朝青龍に対し「ベビーフェイス」白鵬のイメージで見られるようになる。
やがて白鵬は朝青龍に取って代わり、2010年に朝青龍は引退。相撲界は白鵬時代となる。
優勝を重ね、双葉山に迫る連勝も記録する白鵬。朝青龍とは違い、あくまで「優等生」だったが、上位を琴欧洲、日馬富士、把瑠都、と外国人力士が占めるようになっていくに及び、次第に「やはり日本人の横綱が欲しい」という声が高まってくる。
多年相撲放送を担当した元NHKアナウンサーで相撲評論家の杉山邦博氏によると、白鵬は意外にそういう声を気にするようだ。「一番、大相撲を支えているのは自分なのに、という思いがあるのでは」と杉山氏は語った。
●稀勢の里の台頭
そして2013年九州場所「事件」は起きた。
●白鵬に感じる複雑な思い
この「大達羽左ェ門」さんの連続ツイート、必ずしも全てに同意はしないが、白鵬の成長の跡を振り返ったものとして興味深い。
この中で大達さん(このハンドルネームは元々明治期の強豪大関のしこ名)は、次のように指摘する。
「私はこの時期の白鵬の土俵を好まない。しかし、その背景にあったであろう白鵬の精神状態には一考の余地があるように思われる。稀勢の里の台頭、横綱挑戦と共に白鵬の土俵が荒れていくように見えたのは偶然だろうか」
私も白鵬の相撲には基本的に批判的だ。
それでも、批判しながらどこか引っかかるものを禁じ得ない。
これほど複雑な思いにさせられる力士はいなかった。
横綱相撲とは――「横綱白鵬"孤独"の14年」を見て
(以下、写真は同番組から画面を撮影したもの)
番組中「横綱の品格とは」と問われて「鬼のように勝ちに行き、土俵を降りれば優しく」
と答える一方「横綱相撲とは」との問いには「勝つこと」と答えた。
「いくらいい横綱でも、優しくても、土俵で結果を出せなかったら引退しかない」と。
●大鵬の言葉
白鵬は双葉山を目標にしたとしばしば言っている。この番組の中でも「こういう横綱を目指したいという気持ちがあった」と語った。
だが双葉山よりも、どちらかというと親交のあった大鵬の影響の方が強かったような気がする。
その大鵬の言葉で最も衝撃を受けたのが「わしは横綱になったとき『引退』のことを考えていた」だった。
大鵬の相撲は、くの字型に腰を引いて無理をしない「負けない相撲」と言われ、それに対しては「退嬰的な『小さい相撲』だ」という批判もあった。
大鵬の「負けない相撲」、白鵬の「勝ちをもぎ取る相撲」、真逆のようだが、「横綱は負けてはならない」と「勝たねばならない」はコインの裏表だったのではないか。共通していたのは「勝敗へのこだわり」だったと言えるかも知れない。
その後、「勝たねばならない」という思いばかりが、いわば独り歩きを始めたように思える。生々しい言い方をすれば白鵬の中で「勝たねばならない」という観念ばかりが肥大化していったような・・・。
大鵬が存命なら「そういうことじゃないんだ」と言ったかも知れない。しかし大鵬もすでに亡く、貴闘力も指摘していたが、横綱学とでもいったものを指南してくれる人も身近にいなかった。
●もし双葉山と会っていたら
白鵬が関心を寄せた双葉山が、最もその真価を発揮したのは六十九連勝当時ではなく、その三、四年後、1942~43年に四連覇した時期、ことにその後半、二場所連続全勝の時だと言われる。そこにおいて受けて立つ立ち合いの極致「後の先」を完成させたと。
だが、翌1944年には、衰えを見せ始める。「受けて立つ『後の先』の立ち合い」は、気力、体力の充実しきっている時には無敵の強さとなって表れたが、衰えるとその虚を突かれることになる。同年夏場所、照国に寄り切られた相撲はその典型だった。
「受けてばかり立つのは無理だ」
「角界最高峰の横綱として、相手の声で立つのはいかにもしかるべき矜持だが、下位の者はともかく、同格の者には無理が生じる。仕切りの時間を一貫して気力を充実させることは至難の業で、しかも相手は自分の気合が満ちたとき、その虚をついて立ってくるのであるから、当然悪いところでも立たなくてはならない。双葉山の信念は首肯できるが、それに膠着せずに考えてもいいのではないか」
もっともな見方であるが、双葉山はその立ち合いを変えなかった。勝つがための立ち合いはしなかった。相手の声を受けて立つことを変えようとはしなかった。ただし、それを支える気力が衰えてきたことは否めない。それをもってよしとしていたであろう。
自分の相撲が通じなくなってきたら、それを是非なしとした双葉山。「勝たなければならない」しかし「勝てなくなってきた」そのとき相撲ぶりを変えてなりふり構わず、もぎ取るように勝ちを掴みにいった白鵬。両者の「勝負哲学」の違いといえばそれまでだが・・・。
【若手が信頼してぶつかっていった】
双葉山で、もうひとつ触れておきたいのは「対戦相手が信頼してぶつかった」こと。
1940年代、豊島という力士がいた。東京大空襲で25歳の若さで死去したが、生きていれば大関は望めた。兄弟子の安芸ノ海などは「あいつが生きていれば横綱になれただろうな」と言ったほどの有望力士だった。
その豊島の、1944年夏場所での羽黒山戦と双葉山戦を小坂秀二氏は、こう比較している。羽黒山も当時の横綱。同じ立浪部屋で対戦はなかったが、双葉山に次ぐナンバー2の強豪横綱で、双葉山が衰えた後は第一人者となった。全盛期が戦中、戦後の混乱期でなければ、もっと活躍していただろう。そういう力士である。
・・・豊島の相撲を見ると、双葉山との相撲と羽黒山との相撲は明らかに違うのである。双葉山に対したときは、全身をぶつけて、なんの迷いもなくぶつかっている。
ところが、羽黒山に対したときは、そこまで思い切ってぶつかっていないのである。おそらくそれは「ひょっとしたら変わられるのではないか」という不安であろう。この一抹の不安が、豊島の出足を十分なものとはなし得なかった。
双葉山のときはそういうものが一切ない。全身をもってぶつかっていけば全身で受け止めてくれるという信頼感が見受けられる。こういう気持ちでぶつかっていくのだから、その威力、迫力は大変なものである。(中略)それほど、豊島が自分の全力を、安心してぶつけていけるほどの信頼感を持てる相手というのは、相手として最高のものではあるまいか。
(『わが回想の双葉山定次』262~263ページ)
双葉山に対しては、若手は思い切って自分の力をためすことができた。そして小坂氏によると、こういう思い切って当たってくる、いわゆる「タチのいい」力士に、時には負けることを双葉山は喜ぶようなところがあったという。「この野郎、ガイにしやがって」と笑っていた、と。双葉山は本場所の土俵で若手を育てたと言ってよい。
白鵬は、立ち合いのカチ上げで相手を昏倒させたことがあった。これは「育てる」どころか「相手を壊す相撲」だ。むろん対戦力士は脅威を感じただろう(白鵬が若い伸び盛りの時なら、それもいい)。
双葉山と白鵬、どちらが強いか知らない。しかし、私が白鵬が双葉山に及ばなかったと見るのは、こういうところにもある。横綱は勝たねばならない、強くなくてはいけない、それはその通りだが、その先にあるものは白鵬の視野にはなかっただろうか。
もし白鵬が横綱になったとき、教えを請いに訪れたのが大鵬ではなく双葉山の時津風だったら、また違った境地に達していたのではないか――時代的にあり得ないことだが、そんなことも考えてしまう。
* * *
とにかくも、正代戦の突飛な立ち合い、そして千秋楽の照ノ富士戦での張り手、カチ上げを置き土産に、この稀代の横綱は土俵を去った。あれが俺の相撲の集大成だというように――。
* * *
番組の中で白鵬は双葉山について、「今から相撲を取るという顔をしていない」「何で人間がこんな顔になれるんだ」と語っている。
送り吊り出し?――決まり手の名称を考える
《相撲四十八手ならぬ八十二手》
2001年より、それまで七十手だった大相撲の決まり手に、新たに十二手が加えられ、八十二手となった。
七十手では分類しきれないものを加えたのだが、中には「?」と思うものがなくもない。
《送り○○》
その前に、改訂以前からあった「送り出し」だが、これはご承知のとおり、相手の背後について、土俵外に出す技。
相手が出る前に倒れれば「送り倒し」になる。
『大相撲の事典』澤田一矢著/東京堂出版28ページイラスト
この「送り倒し」は七十手のときからあった決まり手だが、この名称には何だか落ち着かないものを感じていた。
なるほど「押し出し」にならずに相手が倒れれば「押し倒し」、「突き出し」に対して「突き倒し」、「寄り切り」に対して「寄り倒し」とくれば、「送り出し」に対応するのは「送り倒し」だというのは一応の理屈ではある。
対面して粘る相手ではなく、人間の通常の進行方向に向けて、相手と同じ方を向いて、土俵外に出すのを「送り出し」と付けたセンスはなかなかだと思う。
日常語でも、人を見送ることを「送り出す」と言ったりする。
だが、その形で倒れたから「送り倒し」というのは、木に竹を接いだ感じがしなくもない。
ましてや、八十二手になってから追加された、
「送り投げ」
「送り引き落とし」
「送り吊り出し」
「送り吊り落とし」
「送り掛け」
等々、相手の後ろからの技は何でも「送り~」にしてしまうのは、どうも取って付けた感がある。
今場所五日目、宇良が大栄翔に「送り吊り出し」を決めた。
NHKテレビより画面を撮影
これは、俵を背にした状態からクルッと回って吊り出したのだから、なおのこと「送った」感が薄い。
相手の前でも後ろでも「吊り出し」でいいのではないだろうか。
「送り吊り落とし」も同じ。
前述の「送り倒し」も「押し倒し」「突き倒し」「寄り倒し」等でいいと思う。
「送り引き落とし」は進行方向とは逆の方向に倒すのだから、これまた「送った」感じではない。
単に「引き落とし」でも良いが、昔「後ろ引き落とし」という手があったというから、それを適用してはどうだったろう。
「送り投げ」は、これも昔の決まり手「抱え投げ」の方がいい。
月刊『大相撲』(読売新聞社)1981年夏場所総決算号「夏場所熱戦グラフ」より。後述するように『大相撲』誌は協会発表にこだわらず、独自に決まり手を掲載していた。
お前の語感の問題に過ぎないと言われるかも知れない。
しかし無闇に新しい名前を付けるより、由緒ある(?)技名を復活させたほうが風情があるというものだ。
それに、決まり手の数を増やしても対応できない決まり方というのは、どうしても出てくる。
例えば、昨日の記事でも言ったが、七日目の大栄翔-霧馬山戦の決まり手を「引き落とし」というのは、どう考えても無理がある(写真参照)。
NHKテレビより画面を撮影
《メディアは協会発表にとらわれなくても良いのでは?》
協会が公式に決まり手を設定する以前は、各新聞で記者が決まり手名をつけて載せていたという。
決まり手制定後でも読売『大相撲』などは、80年代くらいまでは協会発表にこだわらず、独自に決まり手を決めて「かっぱじき」「上手寄り投げ」「外網打ち」等の技名を採用していた。
(今でも解説者などが「かっぱじく」という言い方をすることがあるのだから「かっぱじき」は復活させてもいい)
「送り掛け」は、「後ろ外掛け」「後ろ内掛け」・・・これは、いま私が考えた名称で、いわれも何もないが「送り掛け」よりは無理がないと思う。
各メディアが工夫すれば面白いかも知れない。
相撲甚句「四十八手」に「♫まこと込めたる贈りもの/送り出したらうっちゃられ」という件がある。「送り投げたら」相手は怒るよね。
さらば白鵬 さらば「双葉山」の夢
十二勝という成績も見事だったが、それだけではない。
朝青龍以上の素質だということはすぐわかった。
これは大相撲史上最強と言われる力士になるのでは――と、そう思った。
この力士を注目しないわけにはいかなかった。
「好き」になったというより「期待していた」と言った方がいいかも知れない。
当時、北の富士勝昭氏は白鵬を「悪くても横綱」(最低でも横綱にはなる、の意)とまで評した。
▼理想は「後の先」の立ち合い
横綱相撲は、力士の個性によって色々あっていいと思う。
典型的には双葉山の「受けて立つ『後の先』の立合い」が挙げられるところだろう。
しかし、千代の富士のような鋭く踏み込んで前ミツを取っての出足というのもある。
それが千代の富士の横綱相撲。千代の富士に「後の先」を求めても無理だ。
でも白鵬にはできたと思う。
白鵬には格好の目標だと思った。
白鵬が「後の先」の立ち合いを体得すれば、七十連勝も可能だったのではないか。白鵬はそれができる力士だったはず。
双葉山のような大横綱、しかも双葉山以上の大横綱、白鵬ならなれると思った。
(上はDVD「大相撲名力士風雲録1双葉山」下はNHKテレビより、画面を撮影。双葉山は1939年春、竜王山との対戦。双葉山六十九連勝目の相撲。下は2013年秋、勢戦。この頃の白鵬は張り差しやかち上げは用いず、主に左で踏み込んで上手を取りに行く相撲だった)
▼「相撲への執念」を燃やして欲しかった
今年名古屋場所での優勝のとき「白鵬の勝負への執念」という言葉をよく聞いた。
だが、今どき綺麗事に過ぎると言われるかも知れないが「勝負」ではなく「相撲への執念」を燃やして欲しかった。
自分の相撲を取り切る事への執念。
勝負は後からついてくる、と。
それは、あんな相撲ではなかったはず。
白鵬が双葉山ゆかりの地で 土地の大横綱と同じ いわゆる「雲竜型」の土俵入りを行った映像 私はこちらの方が似合っているように思える
双葉山の再来にして双葉山以上――を期待したが、それは叶わなかった(少なくとも私はそう思う)。
もはやそれは望めなくなっていたが、せめて今年の名古屋場所で受けた批判にどう応えていくか、秋場所で最後にそれを見たかったと思う。
▼一つ引っかかっていること
一つ、白鵬に同情するなら、彼は自分が活躍することが、この国では必ずしも歓迎されていないことを感じていただろう。
大相撲に一番貢献しているのは俺なのに、という思いがあっただろうことは十分想像できる。
そんなことが白鵬の心を屈折させていたかも知れないとは思う。
(長年、相撲放送に携わった元NHKアナウンサー・杉山邦博氏によれば、白鵬は「日本人の横綱がいないのは寂しいね」といった声を、意外と気にするらしい)
* * * * *
白鵬の部屋にはチンギス・ハーンの肖像と共に双葉山の写真が掲げてある。
NHKテレビ「大相撲どすこい研」より 画面を撮影
千代の富士の先祖に横綱がいた!?
子どもの頃に買った本『燃えよ!千代の富士』(講談社)。
当時は(今でも?)こういう厚めの子ども向け文庫サイズ「百科」本というのがよくあった。
●横綱 嶽の浦?
その中に気になる記述が。
千代の富士が100の質問に答えるというコーナーの99問目(185ページ)。
(余談だが、千代の富士が「そおなんです、川崎さん」と言っているのは、質問している記者の名前が川崎だったのではなく、当時のワイドショーから出た流行語「そうなんですよ川崎さん」で、漫才コンビ「ザ・ぼんち」がネタにしていたものだろう。千代の富士がよく「ザ・ぼんち」の物真似をしていたというのは、妻の久美子さんも相撲誌のインタビューで話していた)。
いや、しかし歴代横綱の中に「嶽の浦」なんて力士はいないはずだが・・・?
(参照)↓
しかし、この本には写真まで載っていて「ひいおばあさんの弟」と説明がついている。
●ヤフー知恵袋に質問
子どもながら疑問に思っていたが、この本が出てきたのを機に「ヤフー知恵袋」に質問してみることにした。四十年来の謎が解けるか。
一つ目の回答
すると早速「江戸末期~明治にかけての津軽藩の力士で、強すぎたため妬みを買って毒殺された」という回答をいただいた。実は、その話も、この本の中に掲載されている「北海のウルフ 千代の富士貢物語」という漫画の中に紹介されている(61ページ)。
ちょっとフィクションのにおいがする話だが、それはともかく、これがその「嶽の浦」だとするには、少し問題がある。
嶽の浦は「ひいおばあさんの弟」とのことだから、千代の富士の父の秋元松夫さん(1999年没/74歳)の年齢から逆算すると、やや古く見積もっても、曾祖母は明治初期の生まれと考えられ、その弟なら、江戸末期から明治にかけての力士というのは、ちょっと時代が古い。しかし同一人である可能性が全くないとも言えない。
二つ目の回答
さらに続けて別の方からいただいた回答には、1994年にNHKテレビで放送された「スポーツ100万倍」という番組の千代の富士が取り上げられた回で、嶽の浦のことが紹介されたことがあるという。しかも、やはり毒殺されたという津軽藩の力士がそれだと。
しかしNHKで紹介されたとはいえ、歴代横綱に嶽の浦という名がないという事実は動かない(もっとも上記リンク先のNHKホームページでは、嶽の浦のことを「横綱」とは言っていないのだが)。
この方は「大坂相撲や京都相撲の非公認横綱の可能性もあるかと思いましたが、該当する力士はいませんでした」とも付け加えている。
●謎は残る・・・
そもそも、いくら検索しても「嶽の浦」という力士の情報自体が見つからない(明治末期に「嶽ノ浦」という一字違いの力士はいたようだが、序ノ口でひと場所取っただけで引退しており、しかも東京都出身とのことなので、関係はなさそうだ)。
別の力士のエピソードが紛れ込んだ?
いろいろキーワードで検索を続けたところ、江戸時代の大関「白川志賀右衛門」にも毒殺されたという伝承があり(しかも殺害された場所は「津軽藩」だという。白川自身は秋田藩の出身らしいが)これが「嶽の浦」のエピソードとして伝えられるようになったということも・・・?。
(参照)↓
疑念は尽きないが
疑い出せば、そもそも「嶽の浦」という力士は実在したのか、この力士の写真は本当に「嶽の浦」のものなのか、なぜ「横綱」だったとされているのか。実在したとして、本当に千代の富士の先祖なのか―――疑念は尽きないが、千代の富士の生家・秋元家に、こういう伝承があるということだけは確かなようだ。
しこ名の怪
小錦
今のように外国人力士が多くはなかく、むしろ珍しい時代で、同じハワイ出身の高見山が同郷からスカウトして来たということもあり、入門時から話題になっていた。
新弟子としては規格外の体格も注目されていたが、高砂部屋ゆかりのしこ名「小錦」と命名されたと聞いたときは「あの巨漢に『小』錦はないんじゃないか」と思った。しかし、後に史上最重量力士となると、しこ名とのギャップがかえって面白かった。
同時代の幕内には「大錦」がいたのも、また面白かった。牧伸二が「大錦より小錦でかい♫」などと歌っていたことがある。
小錦(『歴代大関大全』ベースボール・マガジン社/巻頭口絵写真)
北勝海
関脇までは本名の「保志」で取っていたが、大関昇進を機にしこ名を付けることになる。
よく知られた話だが、本人は出身地の「十勝」をしこ名に取り入れたかったものの「10勝」では優勝できないと師匠が難を示して、北海道の「北」に十勝の「勝」を合わせて、しかも「勝」を「とかち」の「と」と読ませるウルトラCで「ほくとうみ」と名乗った。苦しい読みだが、当時は漫画の「北斗の拳」がブームだった頃で、かっこいいと思ったものだった。
北勝海(『歴代横綱71人』ベースボール・マガジン社/41ページより)
なお「勝」は「とう」で「海」は「み」と読み「北勝海」は「ほく-と-うみ」ではなく「ほく-とう-み」だとする説も現役の頃からあったが、これは後付けではないだろうか?
もし、そうだとしたら今の「北勝富士」は「ほうとうふじ」にならなければならない理屈になる。これを「と」と読ませているということは、やはり「ほく-と-うみ」のつもりだった可能性が高いと思う。北勝力は「とう」の読みだったが。
北勝海一代限りの読みなら、どうしても郷里の名を入れたかったという気持ちもわかるが、弟子にもとなると、あまり漢字の読みを新造しないでほしい気もする。
玉の海
相撲解説者の玉の海梅吉は、現役名は「玉ノ海」だったが、解説者としては「玉の海」を名乗っていた。
今は、解説者としての玉の海について書かれたものも「玉ノ海」と表記しているものが多いが、NHKテレビの字幕で「の」となっていたのをはっきり覚えているし、当時の出版物を見ても「玉の海」となっている。
なぜ「玉の海」なのか――以前、ヤフー知恵袋に質問を投稿したところ、玉ノ海梅吉の弟子だった玉乃海代太郎(太三郎)が、一時期「玉ノ海」と名乗っていたことがあり、玉の海の解説者就任がその時期に重なっていたので、現役力士と同じ名では具合が悪いということで「玉の海」になったのではないかとの回答をいただいた。確証には欠けるが、可能性のある話だと思ったのでベストアンサーに選んだ。
それにしても、横綱玉の海は、本人の希望で玉乃島から改名したと聞くが、なぜ師匠の「玉乃海」ではなく、解説者の「玉の海」と同じ字にしたのだろう?(ご存知の方がいらしたら、お教え下さい) 解説の玉の海さんも、孫弟子に当たる横綱玉の海に期待してかわいがっていたらしいが。
当時の相撲放送や相撲誌は、ややこしくなかっただろうか。
「玉の海さん、今場所の玉の海はどうですか」なんてこともあったわけだ。
(月刊『大相撲』読売新聞社/1982年夏場所総決算号72ページ「総評座談会」。「玉の海」となっている。なおこの座談会は、いつもは写真のメンバーに加えて天竜三郎氏が参加していたのだが、この号では、たまたま体調不良で欠席。錚々たる顔ぶれだった)
相撲界を追われた横綱二人 ② 双羽黒(北尾)
千代の富士全盛期 最大の強敵
ついに1回も優勝はできなかったが、80年代後半の、全盛期に向かう千代の富士と最もいい勝負をしていたのが双羽黒=北尾(対千代の富士戦6勝8敗。もっとも他に優勝決定戦で2敗しているが、それは千代の富士との同点が2回もあったということでもある)。
大相撲には「準優勝」を表彰する制度はないが、優勝次点、または同点が合わせて7回。
双羽黒(右)対千代の富士(写真はすべてNHKエンタープライズ「昭和の名力士 六」より画面を撮影)
横綱昇進時に、それまでの本名の「北尾」から、春日野理事長から、立浪部屋ゆかりの二人の横綱、双葉山と羽黒山の名を取って「双羽黒」の四股名を送られたことからも、いかに有望視されていたかが伺える。
(私の父が「四股名だけなら史上最強だな」と言っていた。ただ私は、同様に二人の四股名をミックスした千代の富士[千代の山+北の富士]がすっきりまとまっていたのに比べると、いかにも二つの名前をくっつけた、いわゆる木に竹を接いだ感じで、あまりいいとは思わなかった)。
あのような形で引退(当時の用語では廃業)しなければ、千代の富士と時代を二分していたかも知れないし、のちに台頭してくる貴乃花の壁となって立ちはだかっていたかも知れない。
最後まで大相撲を好きになれなかった
だが、この人の場合、相撲の才は類を見ないものだったが、相撲界という場所には向いていなかったとしか思えない。
相撲評論家・小坂秀二は「・・・私は、北尾には、どこか信頼し切れないものを感じていた・・・相撲に自分を賭けている姿勢が感じられな」かったと記している(『昭和の横綱』冬青社264ページ)。
それは、逆に双羽黒の側から言えば、どうしても大相撲というものが好きになれなかったのだろう。
幕下時代から有望視されながら「すぐいなくなったり、相撲界で言う「イタイタ(痛痛)を決めこんで休んでばかりだったので(幕下で)三年もかかった」(『昭和の横綱』264ページ)ことからも見て取れる。精神力が足りないといえばそれまでだが、小坂も「相撲界そのものが嫌いだったのだろう」と言う(同267ページ)。
そんな好きでもない相撲界の最高位に、千代の富士の一人横綱が続き、次の横綱が欲しい協会の、多分に政策的な事情で上げられてしまったのは一種の悲劇だった。
彼を活かす道は全く違うところにあったのではないか
ただ、小坂がさらに続けて「プロレスに入ったり『冒険家になる』とわけのわからないことを言ったりして、結局何一つまともな結果を生んでいない。何事にも打ち込めない、本気になれない気の毒な性格なのであろう」(268ページ)と言っているのには同意しない。
中学卒業と同時に角界入りし、他の世界を知らないまま一人で生きていかなければならなくなったとき、恐らく何をしたらいいかわからず「スポーツ冒険家」という「わけのわからないこと」をしてしまったり、力士の転向の定番だったプロレス入りなどしたが、他に彼を活かす道があったと思う。
【実は物静かな人?】
多分、当時の力士には珍しかったと思うが、現役の頃から趣味はパソコンで、サバイバルナイフの収集などもしていた(ナイフの手入れをしていて、手を切ってしまったということもあった)。立浪部屋の個室には大きなテレビと音響装置があったのを当時の相撲番組(「OH!相撲」)が紹介していたのも覚えている。
あの巨体からは想像しにくいが、性格的には、相撲はもとより、体育会系向きではなく、インドアで一つのことに打ち込むというタイプだったのではないだろうか。なまじ体があり、体力もズバ抜けていたために、当人にしてみれば不本意な道を歩まざるを得なかったのかも知れない。
後半生は寂しかった印象だが、その彼に、このような家庭があったことには救われる思いがする。↓



[雑誌] 横綱白鵬引退記念号[別冊付録:特大ポスター](相撲2021年11月号増刊)[雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51w44oPxRcL._SL500_.jpg)